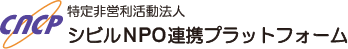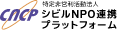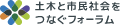CNCPプロジェクト:適疎な地域づくり研究会
シビルNPO連携プラットフォーム 常務理事/事務局長
メトロ設計株式会社 取締役
田中 努
■「適疎な地域づくり研究会」の活動
8月号の冒頭で触れましたが、「適疎な地域づくり研究会」では、ステージⅠでCSVの勉強をして、ステージⅡで、東京一極集中と地方の過疎の問題に関する勉強と議論をし、日本人の人口減少は避けられないので、「関係人口」を増やすには・・、人が減っても住み易い地域とは・・の議論を重ねました。その中で、「適疎」という言葉があることを知り、「過疎の中にも適疎な地域があり、過密の中にも適疎な地域がある」という認識がメンバーに生まれました。そして、ステージⅢで、「提言」をバージョンアップし、私たち独自の視点で、「適疎」に類する好事例だと思われる地域づくりの事例を探しました。
私たちは、土木屋で、しかもほぼゼネコンのベテランの集まりなので、視座・視点は偏っています。多くの地域づくりに関わる社会学・人文学・農政学・・・というような研究者とは、大きく異なる素人ですが、新たな視座・視点を地域づくりに組み込む切っ掛けになれば・・と考えています。
勉強しないと素人の妄想になりかねないので、少し「適疎な地域づくり」に関する研究動向を調べてみました。誤解や不足も避けられないと思いますが、ご容赦願います。
■米山俊直氏の「適疎」
私たちが勉強した範囲では、米山氏が初めて、「適疎」という言葉を使ったのでは?・・と思います。
米山氏は、1930年奈良生まれで、京都大学大学院を修了して、アメリカ・イリノイ大学に留学し、甲南大学助教授・アメリカのアーラム大学教授・京都大学助教授になられた、農林経済学や文化人類学の専門家です。
米山氏は、右の「過疎社会」という著書で、「過疎問題は、単なる政治や経済、あるいは人口論上の問題ではなく、ふかく個々の人間の生きかた、その実存と関わりあった問題だと思う」と言い、過疎現象を文化人類学の立場から検討し、文化変化の理論への接近の手がかりになれば・・と述べています。
耐震技術者の私には、ちと難し過ぎるので中身の解説は省略し、「適疎」の話をします。
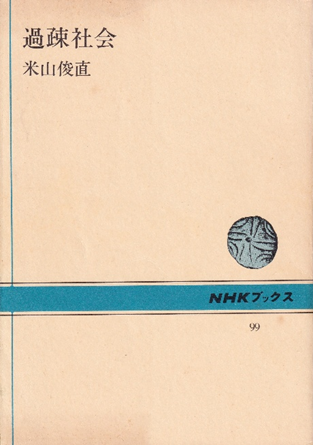
「適疎」という言葉が出てくるのは、残念ながら、「七 おわりに」の、しかも最後のパラグラフ「よりよい対策のために適疎社会をめざして」の締めくくりの言葉として出てきます(笑)。「過疎と一対になっているのは、たいてい過密というコトバである。しかし、ほんとうは過疎の対概念は適疎のはずだ。適当に疎らな人口分布は、人間の生活のうえでもっとも快適なものではないだろうか。過疎社会は、いつの日か適疎社会に転化しうるとするのは、楽観にすぎるであろうか」と。
そして、このパラグラフでは、過疎問題の対策、つまり、過疎の対概念の適疎に向かう方法として、以下の4つを上げています。きっと、この4つは、私たちが「適疎な地域づくり」を考える上でのヒントになると思います。半世紀前の著書であることに配慮しながら。
・対策1:ムラの過去を追わないこと。
ムラつまり行政村内の生活単位である伝統的な集落は、すでにその古いまとまりの機能を殆ど失っている。あるムラに生まれても、早ければ保育所に入る段階から、ムラを超えた場に参加する。今や、それぞれのムラの人々が、自分自身の別の生活圏と関心圏をもち、ムラとの交渉はその一部分にすぎない。ムラを単位にものを考えるのは止めた方がいい。
・対策2:個人の選択を尊重すること。
村人たちが流出するのは、それぞれの個人の意思にもとづいた人生の選択があるからで、それを拘束することは正しくない。職業選択と居住の自由は、国境さえ越えて世界的に承認されるべき基本的人権である。
・対策3:生活は都市との平等を目指す。
物質文化(電気・ガス・テレビ等の家電)という点では、村も都市の平均と比べてそう劣っていない。しかしゴミ処理・汚水処理・医療・娯楽施設など点ではまだ差が大きく、これが改善されれば、村の生活は都市の生活をはるかに上回る環境を生み出せる。
集落の再編成も1つのアイディアである。交通条件が整えば、都市に住み、村は仕事場として「通勤」することも可能になる。
・対策4:あたらしい血を入れる。
過疎社会に新しい秩序を作るためには、これまでの住民だけにこだわらず、その地域に積極的に生きがいを見い出した人々を受け入れ、思う存分活躍してもらう舞台を用意すべきである。外来の人だけでなくUターンやIターンも含め、積極的な援助をすれば、その人たちの創意を活用して、地域社会の発展を期待できるだろう。 ※米山俊直著:過疎社会/NHKブックス99/1969年10月20日/日本放送出版協会発行
■山崎亮氏の「適疎」
ネットで「適疎」を検索すると、CNCP通信の他に(笑)、山崎氏の著書とYouTubeと、次回に予定している摂南大学「適疎戦略研究会」の活動などが出てきます。
山崎氏は、1973年愛知県生まれのコミュニティデザイナーで、京都造形芸術大学の教授です。「人と人とのつながりを基本に、地域の課題を地域に住む人たちが解決し、一人ひとりが豊かに生きるためのコミュニティデザインを実践していて、まちづくりのワークショップや市民参加型のパークマネジメントなど、50以上のプロジェクトに取り組んでいる」そうです。
山崎氏は、大阪府立大学農学部で緑地計画工学を学び、メルボルン工科大学環境デザイン学部でランドスケープアーキテクチュアを学び、大阪府立大学大学院農学生命科学研究科で地域生態工学を修了し、東京大学大学院工学研究科の都市工学で博士(工学)を取得されました。「つながりをデザインする」を志向する工学者で、私たちに通じる感覚をお持ちでは?・・と思います。
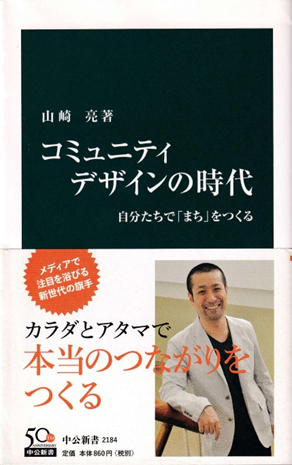
山崎氏が初めて「適疎」という言葉をつかったのは、右上の著書「コミュニティデザインの時代」です。この「第1章 なぜいま『コミュニティ』なのか」の「3 『昔はよかった』のか」の最後のパラグラフとして「『適疎』を目指して」と出てきます。
このパラグラフでは、次のような論旨が展開されています。
東京で暮らして、不動産屋やレストランに給料のほとんどを貢いでいることに疑問を感じた若者が、同等かそれ以上の可処分所得が手に入る田舎での暮らしを目指すのも無理はない。その若者が、例えば、田舎に移ってカフェを始め、材料を地域の農家から調達する。その農家は、都市に輸送する費用が掛からないので従来より適正価格に近い高額で買って貰え、カフェの存在が地方経済に貢献することになる。また、田舎にカフェが出来ると、地域の若い女性たちだけでなく、年寄りたちも店にいることが多く、さらに観光客も立ち寄る。若いオーナーは、こうした人たちに話しかけ、交流を促す。こんな仕事・生活にあこがれる若い人たちが増えているのは、これからの社会にとって希望だ・・と。
このように、地元の産業の様々なところに、都市部からの移住者が入り込み、地元の人たちだけでは出来なかったような新しい取り組みに挑戦する。外から来た人たちも、地元の人たちの協力がなければ無力なので、両者がうまく協働し始めた地域から、人口減少時代の新たなビジョンが示されつつある。しかし、過密であるから成り立っている大都市のビジネスモデルは参考にならず、緩やかに人口が減り続ける地方では、若者と高齢者の関係をうまくつなぎながら、あるいは地域の資源をうまく生かしながら、幸せに暮らしていく方法に関心が集まっている・・と言います。
地域の適正人口規模を見据え、地域でどう暮らしていくのかを考え、それをひとつずつ実践することが重要で、適切に疎らである「適疎」を前提としてまちの将来を考えることが求められる時代になったと言えよう・・と。
この適正人口規模は、人口統計を基に、地元の人口は長い間どれくらいの規模だったのか? 無理せず暮らしていた時代の人口規模はいくらだったか?・・を把握し、将来の人口規模をイメージしながら、今後の生き方を模索するのがいいだろう。そこから新しい地域のイメージが立ち現れるだろうし、新しい日本のイメージが浮かび上がることになるはずだ・・としています。
山崎氏の「適疎」の考えや思いは、下記の2つのYouTubeを見ると、容易に分かります。
YouTubeの「適疎について」の中で、山崎氏は、「過疎と過密の間に、適切に疎らである状態がある」として、勝手に作った造語だと話しています。

都会は、仕事があり、便利でオシャレとかで人が集まってくるが、仕事をしたり住みたい人が多いので住居費が高く、生産地から離れていながら求める人が多いので、新鮮で美味しいものは高い。一方、過疎の地域は、生産地が近く新鮮なものが安価で手に入ったり、比較的広い家に住むことも可能な場所である。
自分がどう生きていきたいのかを考えて、自分にとって「適切に疎ら(適疎)」な場所を見つけるということも大事なんじゃないでしょうか?・・ということを「コミュニティデザインの時代」で書いたそうです。
その後、コロナ禍があって、過密な都会に集まっていながら「三密」を避けることを求められたり、リモートワークで仕事をして会社に行かない生活をして、コロナ前は学校や会社に出かけて夜しか家族全員が一緒に居なかったのに、1日中全員が家に居て「狭い!」と感じるなどで、「適切な疎ら(適疎)」ということを再考するようになったのではないか・・と。
人が少ない地域に住んでいた人達が、都会に近づいてきて、この辺りが賑わっていて適疎だなと思うかもしれない。一方、大都会に住んでいた人が、同じところまで来たら、ちょっと寂しいと感じるかもしれない。適疎か否かは、個人の感覚なので、客観的に数値で表せるものではないでしょう。自分にとって「適切に疎ら(適疎)」であるという地域を見つけたら、きっと住みやすくなると思います。・・と話しています。是非、見てみてください。
※山崎亮著:コミュニティデザインの時代-自分たちで「まち」をつくる-/中公新書2184/2012年9月25日/中央公論新社発行
※YouTube;適疎について:https://www.youtube.com/watch?v=MgM1kLPe8zk
※YouTube;過密でも過疎でもない「適疎」(福井新聞社のインタビュー):
※無印良品「くらしの良品研究所」のコラム「適疎(てきそ)」とは?:
https://www.muji.net/lab/living/210630.html