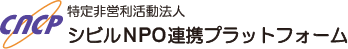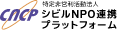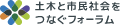CNCPプロジェクト:適疎な地域づくり研究会
シビルNPO連携プラットフォーム 常務理事/事務局長
メトロ設計株式会社 取締役
田中 努
「適疎な地域づくり」の研究動向の2として、本稿では、摂南大学の「適疎戦略研究会」の研究を調べてみました。
■キーマン:野⻑瀬裕⼆氏
今回取り上げる「適疎戦略研究会」は、摂南大学の「地域総合研究所」が2022~2024年度に行った会合で、この地域総合研究所所長の野⻑瀬裕⼆教授が、キーマンと思われます。
野長瀬氏は、東京大学農学部農業工学科を卒業後、早稲田大学大学院理工学研究科工業経営学専攻を修了し、同⼤学院アジア太平洋研究科を修了して博⼠(学術)を取得されています。
その後、埼玉大学地域共同研究センター助教授、山形大学大学院理工学研究科教授、同専攻長を経て、現在の摂南⼤学経済学部教授、同地域総合研究所⻑をされている方です。学外では、産業クラスター推進組織第一号に認定された一般社団法人首都圏産業活性化協会(TAMA協会)の会長として奮闘中とのことです。
野長瀬氏は、ご自分のホームページで、次のように語っています。
グローバル企業群が発展する一方で、企業数や人口の減少が止まらない地域産業が増え、国内産業集積の集約が進行していく圧力を肌で感じる日々です。行政の産業支援策は現在充実していますが、将来的に、行政機関を補う産業支援活動がより求められていくと考えています。私達の世代が、そのための基盤を次の世代につないでいかなければとの使命感を持ち活動を続けています・・・と。
※野⻑瀬裕⼆のホームページ:https://www.innovationpartners.jp/nonagase/nonagase.htm
■摂南大学の「地域総合研究所」
同研究所のホームページによると、目的は、次の通りです。
経済産業・政治行政から、歴史文化、自然環境、都市インフラおよび福祉保健にまで対応できる総合大学の幅の広さを活かした「総合研究」の枠組みを作り、社会連携を推進する機関です。地域の住民・地域における市民活動と行政・福祉のあり方に焦点を置いて、市民社会活性度および地域の課題を各領域にわたって総合的に研究し、政策のありかたを共に考え社会連携を推進します。・・・と。
総合大学の幅の広さを活かし、地域の課題を研究し、政策のありかたを共に考え社会連携を推進するということです。
そして、実際に連携事例として、下記が紹介されています。
| 学部 | 学科 | 実施年度 | 連携先 | 支援内容 |
| 経済学部 | 経済学科 | 2020 ~2021 | 和歌山県由良町 | 由良町の総合戦略に関する学術支援 |
| 2023 | 大阪府寝屋川市 | マーケティング研修 | ||
| 理工学部 | 住環境デザイン学科 | 2022 ~2023 | 和歌山県由良町 | 事前復興計画(案)の作成等 |
| 都市環境工学科 | 2022 | 滋賀県甲良町 | 公共交通のあり方検討支援 | |
| 2024 | 兵庫県神河町議会 | 公共交通のあり方の検討支援 | ||
| 農学部 | 応用生物科学科 | 2022 | 京都府京田辺市 | 農と食を活用した市民主導型まちづくりの推進 -地元産大麦とマコモタケの商品化の試みを軸として- |
| 2023 | 同上 | 京田辺市における縁農ネットワーク形成 ~都市農地で育てる特産物と人財~ | ||
| 農業生産学科 | 2023 | 滋賀県甲良町 | IoTを活用したミニトマト栽培 | |
| 薬学部 | 薬学科 | 2024 | 京都府京田辺市 | 子どもを対象とした植物に関する体験教室の開催支援 |
土木に近い取り組みは、次のような内容でした。
●理工学部 都市環境工学科の公共交通のあり方検討支援
・滋賀県甲良町(2022年度)
コミュニティバスと愛のりタクシーの利用者数や利用区間、時間帯などを分析し、停留所の変更や、ニーズに合わせたルートの提案を行った。
・兵庫県神河町議会(2024年度)
町議会が、町内公共交通のあり方に関する政策提言を行うにあたり、自家用有償旅客運送や自家用車活用事業、公共交通不便地域の扱いなどの現状や課題の説明を行った上で、町内のスクールバスやデマンドバスの運行、利用状況を調査し、町内公共交通に関する提案を行った。
●理工学部 住環境デザイン学科の事前復興計画(案)の作成等
・和歌山県由良町(2022~2023年度)
住民ワークショップを実施し、復興時の具体的な「まちのイメージ」の共有と最終の復興イメージを作るための住民意思を収集。その結果を基に、斜面地集合住宅による建築的高所移転方法を検討した。
※摂南大学地域総合研究所:
https://www.setsunan.ac.jp/rs-collaboration/research/institute/regional/
■「適疎戦略研究会」
摂南大学地域総合研究所のホームページ(上記)では、「適疎戦略研究会」の目的について、次のように記しています。
本学がすでに連携実績を持つ自治体をはじめ、関西地域において問題意識を共有する自治体のネットワークを形成します。また、研究会には本学教員も参加し、課題改善に取り組む自治体にとともに、持続可能な地域経済と生活基盤を創造します。さらに、首都圏産業活性化協会の自治体産業政策勉強会とのネットワークを活かし、元気な地域へのパイプラインを目指します。・・・と。
また、野⻑瀬氏は、自身のホームページで、
2022年度から、適疎戦略研究会を設立し、過疎に悩む自治体、人口減少と産業振興に悩む自治体との連携をスタートさせました。人口を増やそうという努力に加えて、人口は減っていても「仕事が有り、生活の質が保たれた適疎」という状況を求めようという努力が、今後は重要な時代となると思われます。・・・と。
●適疎戦略研究会の会員一覧(2025.1.15現在)合計:関西圏の34自治体+2公益法人等
| 滋賀県:滋賀県、長浜市、東近江市、日野町、甲良町 京都府:京都府、八幡市、京田辺市、京丹後市、木津川市、井手町、笠置町、南山城村 大阪府:大阪府、守口市、寝屋川市、松原市、大東市、門真市、豊能町、河南町 兵庫県:兵庫県、丹波篠山市、朝来市、神河町 奈良県:奈良県、五條市、生駒市、三宅町、高取町、明日香村 和歌山県:和歌山県、橋本市、由良町 政府機関・公益法人等:近畿経済産業局、一般社団法人 首都圏産業活性化協会 |
●適疎戦略研究会の開催状況
第1回適疎戦略研究会(2022.06.30):人口減少の課題を学術面で多角的に支援
–自治体とともに持続可能な地域経済と生活基盤の創造を目指す–
第2回適疎戦略研究会(2022.11.04):「過疎」を「適疎」に転換! 自治体の関心も拡大
第3回適疎戦略研究会(2023.02.03):雇用創出と企業誘致による地方創生
第4回適疎戦略研究会(2023.06.02):「移住定住」や「地域おこし協力隊」の事例発表
第5回適疎戦略研究会(2023.11.02):「ふるさと納税」の事例発表
第6回適疎戦略研究会(2024.02.07):「公共交通」について考える
第7回適疎戦略研究会(2024.06.21):「子育て支援」の事例発表
第8回適疎戦略研究会(2024.12.05):「買い物支援」の事例発表
第9回適疎戦略研究会(2025.02.19):「職員採用‧人材育成」の事例発表
■第1回適疎戦略研究会での話
第1回適疎戦略研究会では、①野長瀬氏から「適疎戦略研究会のコンセプト」が、②特別講演として、総務省過疎対策室の平本課長補佐から「我が国における過疎対策と先進自治体の取組」と題して、人口減少や過疎化の実態と過疎地域における課題解決の成功事例が、紹介されたそうです。
このコンセプトの中では、研究会の取り組みとして、「全国的に進む高齢化や人口減少を受け、本学地域総合研究所では、本学教員が持つ学術的知見を用いて、問題意識を共有する自治体の広域ネットワーク化を図り、課題の把握‧共有や、問題解決に向けた個別自治体への提言を行います。経済学、経営学、農学、看護学などさまざまな分野の教員らが構成員となり総合大学ならではの多角的なサポートを行います。」と述べられたようです。
また、「適疎」の定義が、次のように示されたようです。適疎とは、過疎であり、今後も人口は増えないかもしれないが、人口減少に対して適切な対応をとり、持続可能な地域経済/生活基盤がある状態。
■論文「適疎戦略研究会会員自治体に関する事例研究」の結論
この論文では、研究会の会員自治体の実態調査を行い、それを分析した結論として、下記とその他いくつかが示されています。
1)人口増加率と財政力指数と個人所得は密接な関係を持っている。適疎戦略の起点は「担税力ある住民の確保」であることが判明した。
2)過疎度が上がるほど財政力指数は低くなる。過疎自治体の消滅可能性は高い。過疎度が高い自治体ほど、大学の知や国の支援制度を活用する等努力が求められる。
3)林野比率やアクセス時間等の点で条件が悪いのに過疎指定を受けていない会員自治体がある。会員自治体には過疎指定予備軍が一定数含まれていることが判明した。
4)製造品出荷額等とふるさと納税受け入れ金額の間には相関がある。産業振興・企業育成が長期的なふるさと納税受け入れ額増加には必要である。
5)大都市へのアクセス時間が長いほど人口が減少し、ベッドタウンとしての利便性が小さくなる。大都市へのアクセス時間が短いベッドタウンには、担税力ある住民が存在する。会員自治体を見ると、製造業集積地域より、ベッドタウン地域の個人所得が高い。
※「適疎戦略研究会会員自治体に関する事例研究」野長瀬裕二・久保田誠也、摂南経済研究、第14巻、第1・2号(2024.3)、47~63ページ。
野⻑瀬氏の「適疎」は、ご自身のホームページに書かれている「仕事があり、生活の質が保たれた状態」、少し改まった言い方をすると「持続可能な地域経済/生活基盤がある状態」ということのようです。