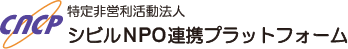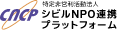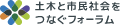「適疎な地域づくり」への提言
―Ver.2 過疎と過密の議論を超えて―
令和7年2月
NPO法人 シビルNPO連携プラットフォーム
適疎な地域づくり研究会
<pdf版>
1.提言のねらい 1.1)
(特非)シビルNPO連携プラットフォーム=略称CNCPは、土木学会の創立100周年を記念した活動から発展した組織であり、建設系NPOや市民組織、建設企業、行政などと協力して、地域社会・市民社会の様々な課題解決を目指しています。
このたび、CNCPの理事と中堅ゼネコン数社で立ち上げた、「土木と市民社会をつなぐ事業研究会=略称CSV研究会」における、研究成果の一部として、我が国が進めている地方創生政策の重要な柱となることを願って「適疎(てきそ)な地域づくり」への提言を取りまとめました。
本提言書における「適疎」な地域とは、それぞれの地域特性を活かした魅力を引き出し、多くの人が“住んでみたい・行ってみたい”と考えるような、過密でもなく過疎でもない地域を指しています。
私たちは今後とも、この国の未来を見据えた「適疎な地域づくり」について、産・官・学はもとより、様々な業種やマスコミの関係者、広く市民社会のご理解とご支援を頂けるよう努力する所存です。
提言のねらいは下記の①~②の通りです。
① 「適疎な地域づくり」に賛同する各地域をネットワークにより結びつけ、それぞれの地域の取り組み内容を共有することで、より一層その内容を充実させること。
② 「適疎な地域づくり」に、産・官・学の主体的な参加を促し、地域づくりに必要な構想・企画か ら実施に至る様々な局面で積極的に支援すること。
* CSV:Creating Shared Valueの略で、共通価値創造と訳され、企業が事業を通じて社会的な課題の解決を図ること。
* version.2は、2023年4月作成した提言案に加筆・修正したものです。
2.適疎な地域づくりを必要とする背景 2.1~12)
「適疎」という表現は、過疎化への対策議論の過程で1960年代頃から使われ出したのではと思われます。令和2年以降のコロナ禍を機に改めて注目されるようになり、今では自治体や研究者、マスコミ報道でもしばしば使われるようになりました。
他方で、「適疎」の両端にある、過疎や過密は古くから論じられ、法的には過疎法(昭和45年)や地方創生法(平成26年)にも、過疎への支援や過密の是正が謳われ、その結果、日本には過密と過疎しかないような錯覚が生まれました。
しかし、地域の皆さんの長年の努力で「適疎」となった市町村は、日本国中に既にたくさんあるのではないかと考えました。そして、そのような既に存在する「適疎な地域」を発掘し、その情報を広め、適疎な地域が日本国中に広まることを期待して、「適疎な地域づくり」に焦点を当ててみたいと考えました。
地方創生法の第一条に“東京圏への過度の人口集中を抑制する”と謳いつつも、第1期計画(平成26年~令和元年)において逆に東京圏への“一極集中が更に加速する”という、悩ましい結果を招いています。更には、この度のコロナ禍で、“人の流れが東京圏から地方圏に向かうかも?”との期待も有りましたが、東京圏への人口集中の流れはコロナ過においてさえ変わることが無いことが示されました。
この国の「政治、経済、教育、文化、情報」の全てを、東京に一極集中させることが、多少の過密のリスクを差し引いても、最も便利であり、最も効率性に優れ、実はそのメリットがたくさんあるという考え方もあります。つまり、無理やり地方分散を唱えてもなかなか実現するものではないと思われます。
このような現実を踏まえ、本提言書では、国民にあまり意識されていないであろう「適疎な地域」の草の根的なネットワークを作り、そのノウハウを共有しつつ、あらたな取り組みを呼びかけ、日本中に「適疎な地域づくり」を推進する運動を起こしたいと考えました。
もともと建設界は、国土づくりに様々なインフラ整備を通じて関わっていますが、「適疎な地域づくり」において、地域の暮らしや経済、福祉、文化など地域社会のこれからを住民と共に考えるとともに、企画・計画を始めとした様々な場面で積極的に関わっていくべきと考えています。
3.適疎な地域のイメージ 3.1~7)
現在、日本は非婚化や出生率の低下、単身世帯の急増等による超高齢・少子化社会が進行し、総人口は2023年1年間で59.5万人(ひとつの県に相当)減少しており、毎年一県のペースで人口減少が進行すると、今世紀の半ばには日本の人口は2/3に、世紀末には1/3と、ほぼ江戸時代の人口へと推移する、そんな未曾有の「激変の時代」を迎えます。
長年束縛されてきた既存の価値観「居住人口を増やそう」、「産業を誘致しよう」、「大都会並みにインフラを整備しよう」から脱皮しなくては、未来を生き抜く新しい発想は生まれないと思います。
そのためには、シンプルに「住んでみたい」、あるいは「行ってみたい」と憧れる、そんな「地域づくり」が必要になると思われます。
このような観点で日本を見わたしたときには、素晴らしい自然環境が享受できるゆとりある空間と時間のある地域、歴史・文化・芸術的に優れたアメニティーが存在する地域、都市機能が充実していて利便性に優れた地域など,様々な特徴を有した地域が存在します。これからの地域の生き残りのためには、人それぞれのライフスタイルに対応した「適疎な地域づくり」こそが、必要になるであろうと想定しています。
4.適疎な地域づくりは誰が担うのか
「適疎な地域づくり」という取り組みの出発点は、まず地域の住民が主体的に取り組むことであると考えます。そのうえで、国や自治体の公的な支援や、外部からの参加者の知恵、大学や専門家等の助言、スタートアップ企業や地銀の参入などその地域の特性に応じた様々な取り組みを積極的に行うことが必要と考えます。
そこで特に留意したいのは、「適疎な地域づくり」に取り組んでおられる皆さんが「心の豊かさ」と「誇り」を持って取り組みに携われる仕組み作りが不可欠である、ということです。その土台として、その地域で安定した生活が可能となる「必要かつ十分な報酬」が得られる仕組みを併せて考えることが必要になります。
建設界には、「適疎な地域づくり」に関わる方々への支援だけでなく、近隣の地域や都市部との連携などを含めた、あらゆる局面への参画の可能性が拓かれます。
5.適疎な地域づくりを全国に広めるには
まずは、CNCPにおいて、既に有るであろう「適疎な地域」、あるいは「適疎を目指している地域」の情報を集め、その成果をCNCPホームページとCNCP通信で発信することから始めたいと思います。
ある程度、地域情報が集まった段階において、緩やかな情報交流を目標に、「(仮称)適疎な地域づくりネットワーク」といった、全国的なネットワークとなることをめざしたいと考えています。
さらに、学協会や国・自治体のみならず、民間企業も巻き込んだ連携を推し進める中で、「適疎な地域づくり」が評価される仕組み作り、社会経済効果、投資を促すための仕組みづくりいった様々な議論へと発展させたいと願っています。
このような過程で、「シビルNPO連携プラットフォーム」の設立当初の役割に照らして、全国のまちづくりNPOと連携した運動に持ち込むことが理想です。
あとがき
我国が陥っている急激な人口減少下においてさえも過疎と過密の拡大が止まらない中で、今こそ「適疎な地域づくり」という発想で、多種多様であってもバランスのとれた地域の発展を実現し、経済的にも精神的にも豊かな私たちの生活が末永く続くことを願っています。
このささやかな提言活動が、「適疎な地域づくり」の進展に少しでも役に立つことを期待しています。
なお、この提言は、研究会メンバーのつたない勉強をもとにしたレポートであり、情報不足、情報の間違いなどは、今後も加筆・修正していく所存です。
お読み頂いた皆様から様々な情報をお寄せ頂ければ幸いです。
参考:図書の他、ネットで得た情報を記載しています。
1.1) シビルNPO連携プラットフォーム「CNCP通信」vol.105 巻頭言
2.1) 米山俊直 「過疎社会」 NHKブックス 1969年
2.2) 山崎 亮「コミュニティデザインの時代」中公新書 2012年
2.3) 無印良品 暮らし研究所コラム 「適疎とは?」
2.4) 毎日新聞 「社説」 2022.1.15
2.5) NHK札幌 ほっとニュース 2022.1.28
2.6) Yahoo!ニュース ちょうどよい「適疎」の町へ 北海道東川町
2.7) 過疎対策法。昭和45年から5時にわたる議員立法による改定
現行:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
2.8) まち・ひと・しごと創生法(通称 地方創生法)、平成26年施行、現在第2期
2.9) 令和4年 中国地方知事会議共同アピール
2.10) 日本総研レビュー 2020.Vol6 no.78 地方創生戦略
2.11) ニッセイ基礎研究所コラム 2022.11総務省「住宅基本台帳人口移動報告」
2.12) 市川宏雄「東京一極集中が日本を救う」ディスカバー携書 2015年
3.1) 東洋経済 ONLINE 2022.1
3.2) 日本総研リサーチ・アイ no.2022.056
3.3) 東京新聞 web2022.7 2022国勢調査
3.4) 総務省人口推計 2022.10
3.5) キャノングローバル戦略研究所 2022.6 厚労省 令和2年 人口動態統計
3.6) 総務省HP意見 持続可能な地域社会総合研究所 藤井浩 2020.1
3.7) 東京都都市整備局 町並み景観プロジェクト
●お問い合わせ窓口
「適疎な地域づくり」は、皆様からの多様なご意見やご提案を歓迎しております。
「適疎」の概念や具体的な地域づくりの取り組みに関するご質問、貴団体での活動事例の共有、連携に関するご提案などがございましたら、下記までご連絡ください。
NPO法人 シビルNPO連携プラットフォーム
「適疎な地域づくり」担当 E-mail:yokotsuka-m@h09.itscom.net