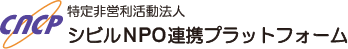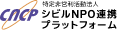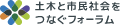適疎(てきそ)な地域づくりとは?
NPO法人 シビルNPO連携プラットフォーム
適疎な地域づくり研究会
適疎という言葉は、辞書にも載っていない造語と思われます。しかし1960年代の文献にも、過密と過疎を議論する中で、目指すべきは“適疎(てきそ)”といった使われ方が見られますので、言葉に表れなくても適疎という概念は多くの方が持ち続けてきたのではと想像しています。そしてその概念が形に表れだしたのは、近年のこと、それもコロナ禍以降のことではないでしょうか。新しい価値観と生活様式の広がりと本格化してきた人口減少への対策などが複合して、新しい視点での地域づくりが顕著になってきたと感じます。
人口減少の影響は、大都市から離れた地域社会で顕著で、その中で、居住人口が減っても、様々な知恵を出して交流人口・関係人口を増やし地域を活性化しようという活動が広がってきました。
過密過疎の議論から解放され、地域の持つポテンシャルを最大限に活かした発想と活動へと転換する。すなわち、それぞれの地域特性をいかした魅力を引き出し、多くの人が住んでみたい、行ってみたいと考えるような地域づくり、私たちはこれを「適疎な地域づくり」と呼んでいます。
もうすこし具体的の適疎な地域づくりのイメージを膨らませて見ましょう。
●住んでみたい、行ってみたい、Well-beingで持続可能なまち、それが適疎な地域。
●暮らす人、訪れる人、親しみを持つ人、応援する人、様々な立場の人たちにそれぞれの適疎がある。
●空き家の再生、商店街の活性化、農林業の産業化、学びを通じた交流づくり、伝統的建物群を活かした観光。~取り組むテーマは様々、都市でも農村でも、地域の特性に応じて~
●適疎な地域づくりの担い手、それは市民、そして地域を愛する皆さん。
●お問い合わせ窓口
「適疎な地域づくり」は、皆様からの多様なご意見やご提案を歓迎しております。
「適疎」の概念や具体的な地域づくりの取り組みに関するご質問、貴団体での活動事例の共有、連携に関するご提案などがございましたら、下記までご連絡ください。
NPO法人 シビルNPO連携プラットフォーム
「適疎な地域づくり」担当 E-mail:yokotsuka-m@h09.itscom.net